シニア世代の親御さんを持つ方必見!高齢者の運転免許返納をスムーズに進める方法と説得のコツ

シニア世代の親御さんを持つみなさん、親御さんが車の運転を続けることに不安を抱えていませんか?高齢ドライバーの事故のニュースが毎日のように聞こえてくると、うちの親もそろそろ運転免許返納のタイミング…?と不安に駆られている方も多いのでは。
しかし、普段から車を活用している親御さんにとっては、「運転免許の返納」=「自由を失う」くらい深刻なこと。ただ心配だからと運転免許を「取り上げる」のではなく、一緒に「より安全な選択肢を見つける」ことが重要なのです。運転免許の返納についてスムーズに話を進めるためには、親御さんの気持ちに寄り添い、納得できる形で進める工夫が必要になります。
ここでは、親御さんの気持ちを尊重しながら、運転免許返納をスムーズに進める方法と、運転免許返納後の生活準備について解説していきます。
高齢者ドライバーの定義
高齢者ドライバーとは、一般的に65歳以上の運転者を指します。警視庁や各都道府県警察の統計でもこの区分が用いられています。
そして車に高齢者マーク(もみじマーク)の提示を努力義務としているのは、実は70歳以上。このマークは過去に枯葉のようだと揶揄されたこともあり、デザイン自体も提示努力義務の年齢も変更された経緯があります。
そして、運転免許更新前に認知機能検査の受験が必要な年齢は75歳以上、と少し複雑なのです。
2021年時点で65歳以上の運転免許保有者は全体の23.5%を占めており、その中でも75歳以上の運転者は全体の7.4%に達しています。
ただ個人差が大きいため、この数字に捉われず親御さんの状況をみて、運転免許返納のタイミングを考える必要があります。
高齢ドライバーの免許返納が必要な理由
高齢になると、身体能力の衰えや動体視力の低下により、ブレーキを踏むタイミングが遅れたり、ハンドル操作を誤るなど、判断ミスが増えて安全運転が難しくなる傾向にあります。運転者本人にそのような自覚があれば良いのですが、若い頃に運転免許を取得して何十年もの運転歴があると、自身の運転技量に自信があり、まだまだ自分は大丈夫という過信につながり運転免許返納を渋るケースもあります。
高齢者ドライバーの死亡事故は、実は車両単独による事故が最も多くなっています。 事故の要因としては、安全不確認による発見の遅れが特に多く、次いでハンドル操作の誤り、ブレーキとアクセルの踏み間違えなどの操作ミスが挙げられます。車の予防安全性能は年々上がっており、自動ブレーキや運転支援システムなど技術の進歩により、近年、日本の交通事故発生件数は減少傾向にあります。
ただし高齢者ドライバーによる事故の割合は年々増加しています。万が一の事故を防ぐためにも、適切なタイミングで運転免許返納を考えることが重要です。
高齢者による重大事故の事例
高齢者ドライバーによる重大事故の事例として、2019年に発生した池袋暴走事故が挙げられます。この事故では、高齢者の運転する車が暴走し、母子が死亡する痛ましい事故となりました。この事故報道がきっかけで、高齢ドライバーの免許返納についての関心が高まり、社会的な議論が活発になりました。
実際にこの事故のあった年は、運転免許返納を検討する高齢者・家族が増え、自主返納が前年比40%増の60万件を超えました。 しかし、翌年以降は落ち着いてきており、高齢者の運転免許返納への意識が社会全体で薄れてきているといえます。
高齢者ドライバーの事故件数と原因
近年、75歳以上の高齢ドライバーによる死亡事故件数は横ばいで推移していますが、全体の死亡事故件数に占める75歳以上の運転者によるものの割合は増加傾向にあります。特に、2021年には75歳以上のドライバーが関与する死亡事故の割合が過去最高の15.1%に達しました。
高齢者の交通事故の主な原因としては、安全不確認が約37.8%を占めており、次いで信号無視や速度違反が続きます。また、75歳以上の高齢運転者は、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故が多く、これは75歳未満の運転者に比べて高い割合を示しています。
親御さんに免許返納を切り出すベストなタイミング
親御さんに運転免許返納を切り出す際は、タイミングが重要です。親御さんとご家族の関係性や、これまでの運転経歴にもよりますが、以下のようなタイミングで切り出すと話しやすくなります。

- 認知機能検査や運転適性検査の結果が思わしくなかったとき
- 運転ミスが増えたと家族が感じたとき
- 親御さんの身近な人(親族や知人)が免許を返納したとき
認知機能検査や運転適性検査の結果が思わしくなかったとき
離れて暮らしている場合やご本人が運転に自信を持っている場合には、プライドが邪魔をしてなかなか結果を聞くことができないかもしれませんが、親御さんが自ら話をしてくれた場合にはとても良いきっかけとなるため、しっかりと運転免許返納について話をしてみましょう。
運転ミスが増えたと家族が感じたとき
親御さんの運転する車に乗る機会は多くないかもしれません。そのような場合には、ドライブレコーダーの設置を提案してみましょう。前方のみ撮影できるものであれば1万円前後で購入でき、取り付けも簡単です。
近年話題に上がることも多いあおり運転の危険性なども話しながら、安全のためにつけておく旨の話をすればスムーズに受け入れてくれるでしょう。
親御さんの身近な人(親族や知人)が免許を返納したとき
これは一番自然に話ができる上、親御さんも非常に受け入れやすいタイミングです。 同世代の方が運転免許返納したことで、「自分も考えなくては」と意識してくれる場合があります。
また、これまで運転免許返納の話題に触れたことがなく、親御さんがどう思っているかわからない場合にも有効です。 この話題を出した際に、運転免許返納を意識したことがあるのかないのか、実は気になっていたけれど、こんな理由で返納できないなど、本音を聞き出すことができます。
親が納得しやすい説得のコツ
運転免許返納を話し合う際に重要なのは、大きく以下の2点です。
- 第三者からのアドバイスを活用する
- 現在の車がある生活から、どう工夫をして車のない生活にシフトしていくかシミュレーションする
第三者からのアドバイスを活用する
運転歴が長く自信がある親御さんの場合は、プライドを傷つけずに伝えることも重要です。「もう歳なんだから運転は危険だよ」ではなく、「家族みんなが安心して過ごせるようにしたい」と伝えてみましょう。
また、家族から言われると反発してしまう親御さんも、かかりつけのお医者さんや他の親族に言われると素直に耳を傾けてくれる可能性も高くなります。
車のない生活をシミュレーションする
移動手段として車が欠かせない存在になっている場合、まずは親御さんがお住まいの自治体で運転免許返納後、どのようなサポート制度があるか確認する必要があります。
一例として以下のようなサービスがあります。
- 運転経歴証明書を提示すると、バスやタクシーの割引が受けられる
- タクシーチケットやコミュニティバス回数券が配布される
- スーパーの配送サービスが無料になる
ただ、自治体の支援制度はばらつきがあり、最大限活用しても車のない状態で快適な生活を送ることができない場合もあります。その際には、家族間で協力できることを挙げてみましょう。
日々の買い物に
- 必要なものを電話で聞いて、家族がネットスーパーや通販で注文する
- 買い物代行サービスを利用する
病院への定期的な通院
- 近隣に住む家族や親族が交代で送迎する
- 福祉タクシーを利用する
- 訪問診療やリモート診療への切り替えを検討する
生活必需品であった車を手放すことは、親御さんにとってはとても大きな決断であり、これまでの生活が大きく変わることになります。
運転免許返納後の生活を具体的にイメージできるように、様々な選択肢を準備しておくことが重要です。

運転免許返納の手続き
運転免許返納の手続きは、警察署や運転免許センターで行うことができます。 申請書を記入し、免許証と本人確認書類を提出することで簡単に申請可能です。
その際、「運転経歴証明書」を発行してもらいましょう。 今後の身分証明書として利用したり、各種サービスを受ける際に必要になる場合があります。
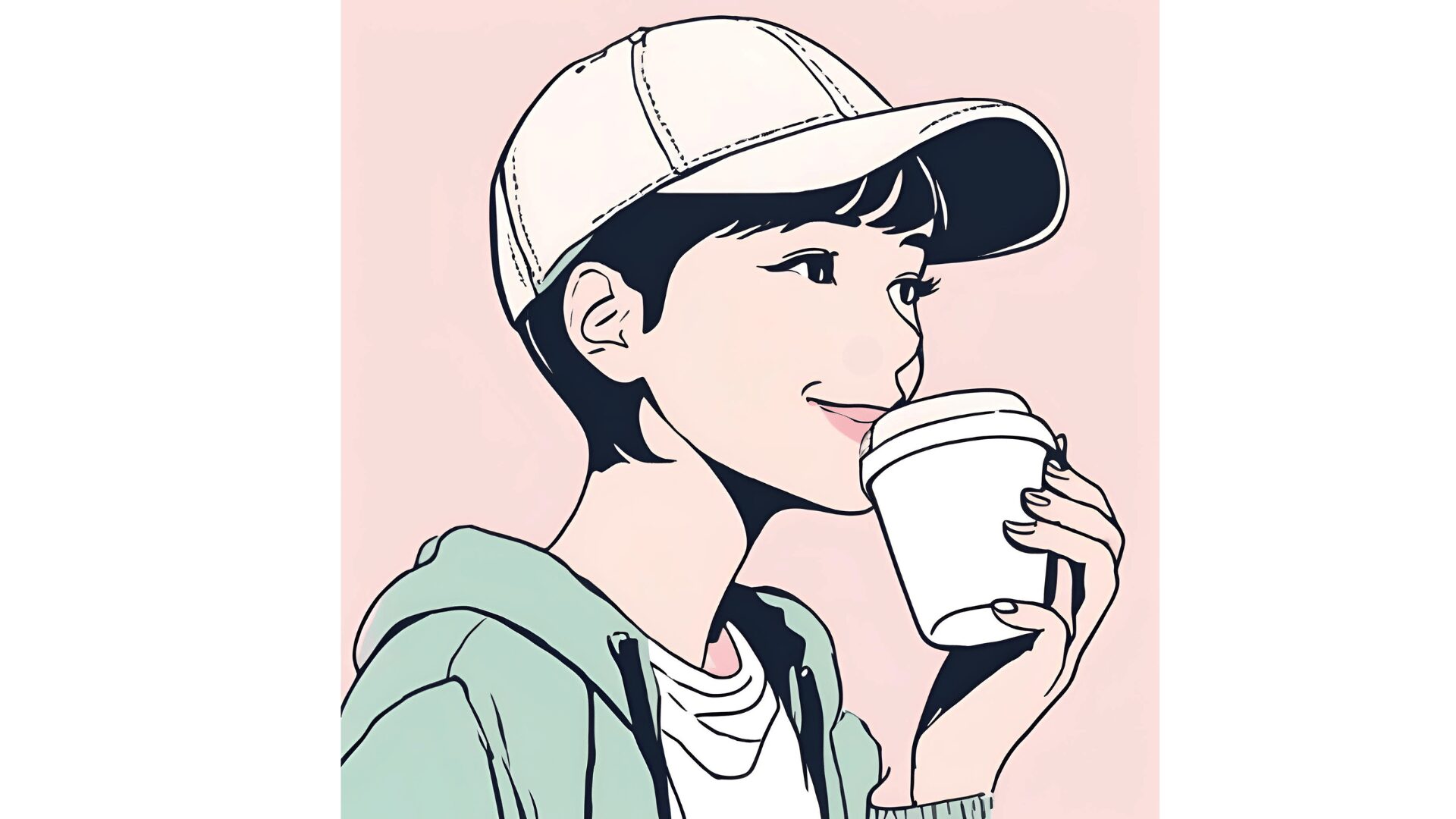
ペーパードライバーだった私の母親も70代前半で自主返納しました。返納をためらっていた理由が、「身分証明書」として便利だった運転免許証がなくなってしまうから。
「運転経歴証明書」が多くの場所で身分証明書として使えると話したところ安心したようで、スムーズに返納してくれました。
運転免許返納の相談窓口
家族で話し合っても、まだ不安が解消されない場合には、各都道府県警察の「安全運転相談窓口」を利用してみましょう。全国統一の相談ダイヤル(#8080)に電話をかけることで、発信場所を管轄する都道府県警察の安全運転相談窓口につながります。
これらの窓口では、高齢ドライバーやその家族が運転に関する不安について相談できる専門職のスタッフ(看護師や医療系の専門職など)が対応してくれます。
相談窓口では、以下のような内容のサポートが受けられます。
- 加齢に伴う身体機能の低下に関する助言
- 自主返納制度の情報提供
- 自主返納後の特典に関する案内
運転免許返納は家族全員でサポートを

高齢の親御さんの運転免許返納は、ご本人にとっても家族にとっても大きな決断ですが、安全な生活を守るために避けて通れない問題です。親御さんの気持ちに寄り添いながら、自主返納について話し合いを進め、返納後の生活のサポート体制をしっかり準備することで、スムーズに進めることができます。
運転免許返納はゴールではなく、新しい生活のスタートです。家族みんなで支えながら、親御さんが安心して暮らせる環境を整えていきましょう。


